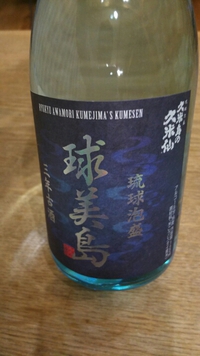2005年09月03日
仕次ぎ
仕次ぎ。
泡盛の古酒(クース)を造る方法として独特な、仕次ぎ(しつぎ)と言う方法があります。

要は、最終的にできあがった古酒に次々と継ぎ足していくという方法です。
ご存じの通り、泡盛は古酒(クース)という味わい方があります。泡盛は一般的に3年以上熟成した物を古酒(クース)と呼びます。蒸留したばかりの泡盛は、味や臭い、くせが強く通常の泡盛でも数ヶ月は酒造所で寝かせてから出荷しています。
新しい泡盛のそれはそれでよいのですが、やはり古酒でしょう。熟成が長くなるほどにコクが出てマイルドになっていきます。本当は、古酒はロックや生で飲むのが良いんでしょう。でも自分はたいてい水割りにしてしまいますが。
熟成するほどに味が出るというのは、ある意味ワインと似ていると思います。
で、古酒の話そのものは別の機会においておいて、古酒の作り方が特徴的です。泡盛には特徴的に仕次ぎ(しつぎ)という古酒の作り方があります。図のように新しい泡盛を何年かごとに甕に貯蔵しておいて、もちろん一番古い物を古酒として堪能します。で、飲んで減った分や自然に目減りした分を次ぎに古い甕から移し、さらに3番目の甕から、・・・というように次々に移して最後に、新酒を入れます。
するといくら飲んでも古酒は減らないという何ともありがたい方法です。
この方が、栓をしたまま寝かせておくよりも古酒に新しい力を与えて、より活性化しておいしくなると言うことです。
泡盛の古酒(クース)を造る方法として独特な、仕次ぎ(しつぎ)と言う方法があります。

要は、最終的にできあがった古酒に次々と継ぎ足していくという方法です。
ご存じの通り、泡盛は古酒(クース)という味わい方があります。泡盛は一般的に3年以上熟成した物を古酒(クース)と呼びます。蒸留したばかりの泡盛は、味や臭い、くせが強く通常の泡盛でも数ヶ月は酒造所で寝かせてから出荷しています。
新しい泡盛のそれはそれでよいのですが、やはり古酒でしょう。熟成が長くなるほどにコクが出てマイルドになっていきます。本当は、古酒はロックや生で飲むのが良いんでしょう。でも自分はたいてい水割りにしてしまいますが。
熟成するほどに味が出るというのは、ある意味ワインと似ていると思います。
で、古酒の話そのものは別の機会においておいて、古酒の作り方が特徴的です。泡盛には特徴的に仕次ぎ(しつぎ)という古酒の作り方があります。図のように新しい泡盛を何年かごとに甕に貯蔵しておいて、もちろん一番古い物を古酒として堪能します。で、飲んで減った分や自然に目減りした分を次ぎに古い甕から移し、さらに3番目の甕から、・・・というように次々に移して最後に、新酒を入れます。
するといくら飲んでも古酒は減らないという何ともありがたい方法です。
この方が、栓をしたまま寝かせておくよりも古酒に新しい力を与えて、より活性化しておいしくなると言うことです。
まあ、一気に飲んでしまっては、さすが仕次ぎでも、なくなってしまうと思いますが、何ともありがたい方法です。
さらに、泡盛は、瓶に詰めた状態でも熟成が進むという不思議な酒です。
ビンテージもののワインのように、記念日などに購入して長期熟成を自分でできるというのも嬉しいですね。
 焼酎熟成サーバー1100cc
焼酎熟成サーバー1100cc
おすすめ度 :
コメント:
 送料無料!焼酎熟成サーバー1100cc+人気の芋焼酎【くろ】720mll付
送料無料!焼酎熟成サーバー1100cc+人気の芋焼酎【くろ】720mll付
おすすめ度 :
コメント:
 瑞泉 古酒 30゜ 青龍 1.8L
瑞泉 古酒 30゜ 青龍 1.8L
おすすめ度 :
コメント:
さらに、泡盛は、瓶に詰めた状態でも熟成が進むという不思議な酒です。
ビンテージもののワインのように、記念日などに購入して長期熟成を自分でできるというのも嬉しいですね。
 焼酎熟成サーバー1100cc
焼酎熟成サーバー1100ccおすすめ度 :

コメント:
 送料無料!焼酎熟成サーバー1100cc+人気の芋焼酎【くろ】720mll付
送料無料!焼酎熟成サーバー1100cc+人気の芋焼酎【くろ】720mll付おすすめ度 :

コメント:
 瑞泉 古酒 30゜ 青龍 1.8L
瑞泉 古酒 30゜ 青龍 1.8Lおすすめ度 :

コメント:
Posted by 泡盛の杜管理人 at 20:55│Comments(3)
│泡盛について
この記事へのトラックバック
自家製古酒の造り方
(5) 時々起こしてあげましょう ただ寝かせておくことより、時々揺すって酒を起こすことも大事な作業になります。
この辺りの段取りが意味深いです。ただ歳をとる...
(5) 時々起こしてあげましょう ただ寝かせておくことより、時々揺すって酒を起こすことも大事な作業になります。
この辺りの段取りが意味深いです。ただ歳をとる...
自家製古酒の造り方 -歳をとるのは素敵なこと?(2)-【退屈な30代が見るサイト】at 2005年09月03日 21:00
この記事へのコメント
泡盛の古酒作りは、なかなか楽しみですよね。
今年の沖縄行きでは、山川酒造の新酒「かねやま」と、やちむんの里の栄用窯の壷を買い、帰ってきて早速を仕込みました。時々揺すっています。来年の仕次ぎの時、飲むのが楽しみです。
泡盛ではありませんが、米や麦の原酒系も、瓶で熟成しているところです。常圧焼酎は、寝かせるとよかですよ~。
芋については、寝かせると香りが飛んだりするようで、3年モノぐらいが限度?みたいですね。芋の魅力をどこに感じるか、によっても違うのでしょうが。
今年の沖縄行きでは、山川酒造の新酒「かねやま」と、やちむんの里の栄用窯の壷を買い、帰ってきて早速を仕込みました。時々揺すっています。来年の仕次ぎの時、飲むのが楽しみです。
泡盛ではありませんが、米や麦の原酒系も、瓶で熟成しているところです。常圧焼酎は、寝かせるとよかですよ~。
芋については、寝かせると香りが飛んだりするようで、3年モノぐらいが限度?みたいですね。芋の魅力をどこに感じるか、によっても違うのでしょうが。
Posted by ショチクレ at 2005年09月03日 22:10
■ショチクレさん
コメントありがとうございます。
「やちむん」というのは、焼き物(やきもん)が語源でしょうか?
自家製で造る場合には、やはり縁の下とか、温度変化が少ない場所に寝かせておくのでしょうかね。ワインとにていますね。
コメントありがとうございます。
「やちむん」というのは、焼き物(やきもん)が語源でしょうか?
自家製で造る場合には、やはり縁の下とか、温度変化が少ない場所に寝かせておくのでしょうかね。ワインとにていますね。
Posted by 泡盛の杜管理人 at 2005年09月04日 10:37
ワインの事はよく判りませんが、一般的には温度変化が少ない所で、と言われていますね。
TVで居酒屋「うりずん」のマスターが、「風通しがよく、カビなどが繁殖しない所。封をする時、石油製品(ビニール)は匂いが移るので、セロハンを使う事。油脂類は厳禁で、手をしっかり洗ってから壷を触る事。」と言われていました。これらを守るようにはしています。
TVで居酒屋「うりずん」のマスターが、「風通しがよく、カビなどが繁殖しない所。封をする時、石油製品(ビニール)は匂いが移るので、セロハンを使う事。油脂類は厳禁で、手をしっかり洗ってから壷を触る事。」と言われていました。これらを守るようにはしています。
Posted by ショチクレ at 2005年09月04日 22:54